日本語教育能力検定試験、どれくらいの期間勉強すればいいんだろう?と悩んでいませんか?
 わたし
わたし「独学3か月で合格!」「半年独学で不合格」などの情報を見ると、私は一体いつから準備したらいいの?とわからなくなってしまいますよね
私はこの試験を受けるのに、あれやこれやと試行錯誤しながら勉強期間を決めました。
たくさんの方が3か月のような短期間で合格している中、自分に合った学習期間を選んだことで、
- 計画に沿ったストレスのない勉強
- テストまでの十分な練習
ができ、結果的に令和3年度の日本語教育能力検定試験合格に繋がったと感じています。
そこで今回は
- 自分に合った勉強期間でしっかり準備したい
- まだ試験までたっぷり時間があるが、いつから試験勉強を始めるべきかわからない
という方に向けて
- 勉強期間を決める際に考慮したポイント
- 私があえて長期学習(10か月)を選んだ理由
を紹介します!
勉強期間を決めるときの考慮ポイント
ここでは自分に合った勉強期間を決めるために私が考慮した点について説明します。
なんとなく勉強期間を決めて
- 時間が足りなくなる
- 無理な計画で挫折してしまう
ということにならないためにも、以下のことを考慮しつつ自分に合った計画を立てましょう!
①バックグラウンド
勉強期間を決めるとき、まず考えたのがバックグラウンドです。
これはつまり日本語教育能力検定試験で問われる知識について現時点でどれだけ知っているかということ。
- 大学で国文専攻だった人
- 言語習得理論について学んだことのある人
- 日本語教育で必要な知識とは全く縁のない生活を送ってきた人
の3者ではもちろん現在持ち合わせている知識量やそのジャンルも異なります。
試験に必要な知識のどれくらいを現時点で知っているのか、赤本を参照しつつ把握するようにしました。
②1週間あたりの勉強に割ける時間
「1週間で○○時間勉強」のように、自身の生活パターンから1週間にどれくらいの時間を勉強に費やすことができるのか算出しました。
ここであえて「平日1時間・休日2時間」のように日単位で考えないのは、
- 日や曜日によって使える時間が違うため
- 「1日○時間」という目標だと、1日勉強しない日ができたときにモチベ―ションが下がりやすいため
です。



「1日〇時間」と決めたほうが私の生活・性格に合っているよ!!という人はもちろんそれでも◎!
- 1週間10時間を勉強に使える人
- 1週間30時間を勉強に使える人
では必要な勉強期間にも大きな差が出ます。
また学生の人は、授業期間と長期休み期間では検定試験の勉強に充てられる時間も変わるはず。
勉強期間の全体像を考えながら、自分の生活スタイルに合わせた、無理のない勉強時間を考えました。
③短期集中型?コツコツ型?
あなたは短期集中型ですか?
コツコツ積み上げ型ですか?



あまり集中力が続かないし、継続が得意だからコツコツ型かな



長期間の勉強は中だるみしてしまうから短期集中!
などなど、性格によってタイプが異なりますよね。
- モチベーションが無くなってしまう
- 集中力が続かない
ということをできるだけ避けるためにも、
自分のペースで効率的に、ストレスなく勉強できるのはどちらかを見極めました。
④自身の体調
自身の体調で不安な点はありませんか?
例えば、頭痛もちの人で考えてみると
「土日は暇だから8時間くらい勉強できそう!」と計画を立てたが、突然のひどい頭痛であまり勉強できずに1日が過ぎてしまった
なんてこともあるかもしれません。
普段の自分の体調を振り返って不安要素があれば、
スケジュール通りにならなくても取り返せるように計画を練ります。
⑤勉強が継続できなくなるハプニングの可能性
人生にはハプニングがつきもの。
例えば学生なら
- 大学の授業課題が想像よりたくさん出た!
- スランプでレポートが書き終わらない!
- 文化祭準備が忙しくて時間が取れない!
などなど。
思った通りに勉強できなかった~!とならないように、
自分の生活で起こり得そうなハプニングを事前に想定して勉強期間を少し長めにとるよう検討することも大切です。
私が長期学習を選んだ理由
私は日本語教育能力検定を2020年の6月に知りました。
令和3年度(2021年10月)の試験を受けるためにどれくらいの期間勉強すべきか悩みましたが、
以上で触れた要素を踏まえて、2020年12月半ばごろからおよそ10か月間の試験勉強をすることにしました。
なぜこのように長めの勉強期間としたのか、以下で1つ1つ詳しく見ていきます。
①バックグラウンド:言語関連の授業を履修した経験あり
私のバックグラウンドはこんな感じです
- 日本語の文法に苦手意識
- 英文科
- 大学で言語関係の授業を履修済
- 英語音声学
- 異文化コミュニケーション
- 第二言語習得
- 社会言語学
- 談話分析
- 英語学概論
よって、以上の分野については見覚えのある単語・概念が多くありました。
ただ、なんとなく覚えているだけで「説明しろ!」と言われたらお手上げです。



それ以外の分野に関しては全く知らないような状態だったので、必要な努力量は大きいと判断しました
②1週間あたりの勉強に割ける時間:授業期間で最低12時間
まず当時の私の生活スタイル(【2020年10月頃】大学3年後期・授業あり)から、1日に割ける時間は、
平日:30分~2時間(曜日によって変動あり)
休日:(少なく見積もって)2時間
と考え、1週間あたりでは、最低でおよそ12時間程度を想定。



実際に1日5分くらいしか見れなかった日には「その週のうちに挽回するぞ!」という気持ちで翌日以降の勉強時間を多めにとるようにしたり、時間に余裕のある時はとにかく勉強しまくったりしていました。
また長期休みは1週間で20時間程度、大学4年後期(2021年9月終盤~)も授業数が減るため、長期休みのペースを維持したまま週20時間で勉強を進めていく計画にしました。
実際に令和3年度試験受験前は
9月:98時間(約22時間半/週)
10月(23日まで):67時間(約20時間/週)
勉強していたので、かなり計画通りに進められていたと思います。
③短期集中型?コツコツ型?:コツコツ型
コツコツ型です。
学生時代、試験1週間前から鬼のように勉強して難なく高得点を取っていく人にたくさん出会いましたが、私はそのような勉強法では全く太刀打ちできません。
集中力が続かないので、長期間かけてコツコツやることに決めました。
④自身の体調:不安要素あり
- 頭痛もち
- 側弯症からくる背中痛
から、集中しづらかったり、酷いときは1日中ぐったりしてしまうときもあります。
これらを考慮して、何も出来ない日が数日続いたとしても巻き返せるような、少し余裕をもった計画を立てるべきだと判断しました。
⑤勉強が継続できなくなるハプニングの可能性:あり
当時の私が思いついたのはこんなことです
- 台湾から日本へ帰国するための手続き、準備
- 感染症に罹ってダウンしてしまう
- 期末試験で検定の勉強どころではなくなってしまう
これらのハプニングすべてが発生しても大丈夫なように、およそ3週間~1か月くらいは勉強期間を多くとるように計画。
幸い感染症に罹ることはありませんでしたが、実際に①と③で赤本の簡単な確認しかできない日がそれぞれ1週間強ありました。



実際にこの約2週間は勉強を進めることができませんでしたが、勉強期間を余分に取ったことで、あまり焦らず、モチベーションも保てたのが良かったと思います。
⑥その他:一発合格必須だった



その他ってなに?!
と思われた方もいると思いますが、上記以外にもそれぞれの事情によって考慮すべき点がある人もいるでしょう。
私の場合は「翌年は受けられないから絶対に一発合格しなければならない」という状況です。
- 翌年に台湾で生活を始める
- コロナや仕事の都合で帰国は容易でないはず
- 金銭的にも受験のためだけの帰国は難しい
以上のような理由から一発合格が必須でした。
そのためにはテストで問われる知識と記憶の精度を限りなく上げ、わからない問題については解けるようになるまで何度も繰り返しやり込む必要があります。
よって勉強期間を更に長く取り、確実に合格しにいくための計画としました。



実際に2020年の12月半ばくらいから赤本で勉強を始め、2021年6月時点で初めて問題集を解いた時には、マークで合格点にギリギリ届かない程度の点数でした。
長めに準備期間を取ったことで、そこから10月の試験まではとにかく過去問と赤本を行ったり来たりして、知識の精度を上げることに集中できました。
まとめ
いかがでしたか?
- 日本語教育能力検定試験の勉強期間に考慮したほうがいいこと
- 試験で問われる知識を現時点でどれだけ知っているか
- 1週間あたり勉強に割ける時間はどれくらいか
- 短期集中型かコツコツ型か
- 自身の体調の不安要素があるか
- 勉強に支障を与え得るハプニングはあるか
勉強に充てることのできる時間、向き不向きは人によって異なります。
自分の生活スタイルや勉強法に合った勉強期間を見つけ、合格に向けて一歩ずつ歩みを進めていきましょう!
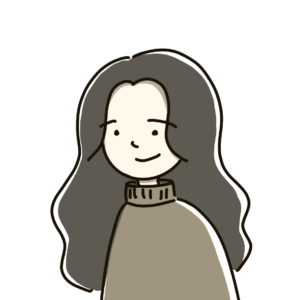
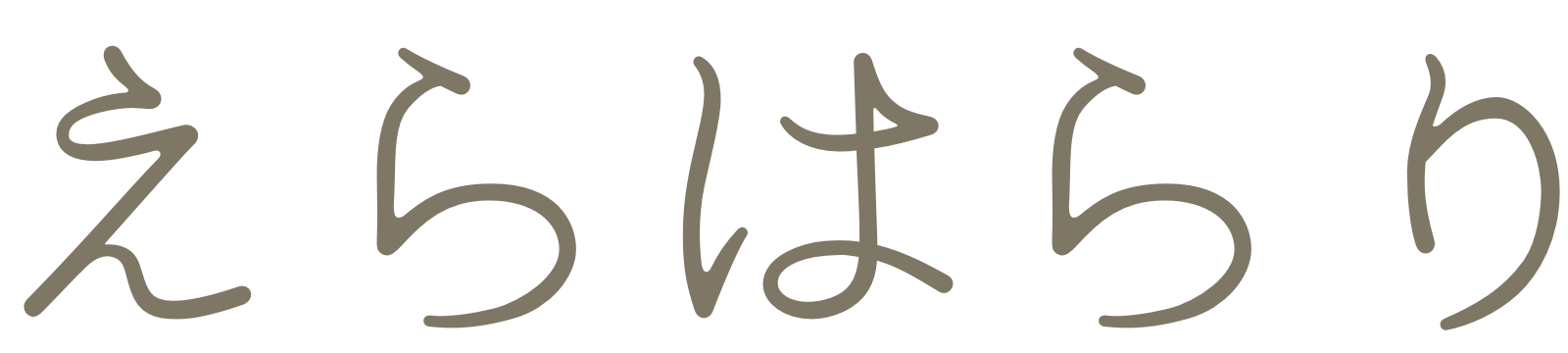
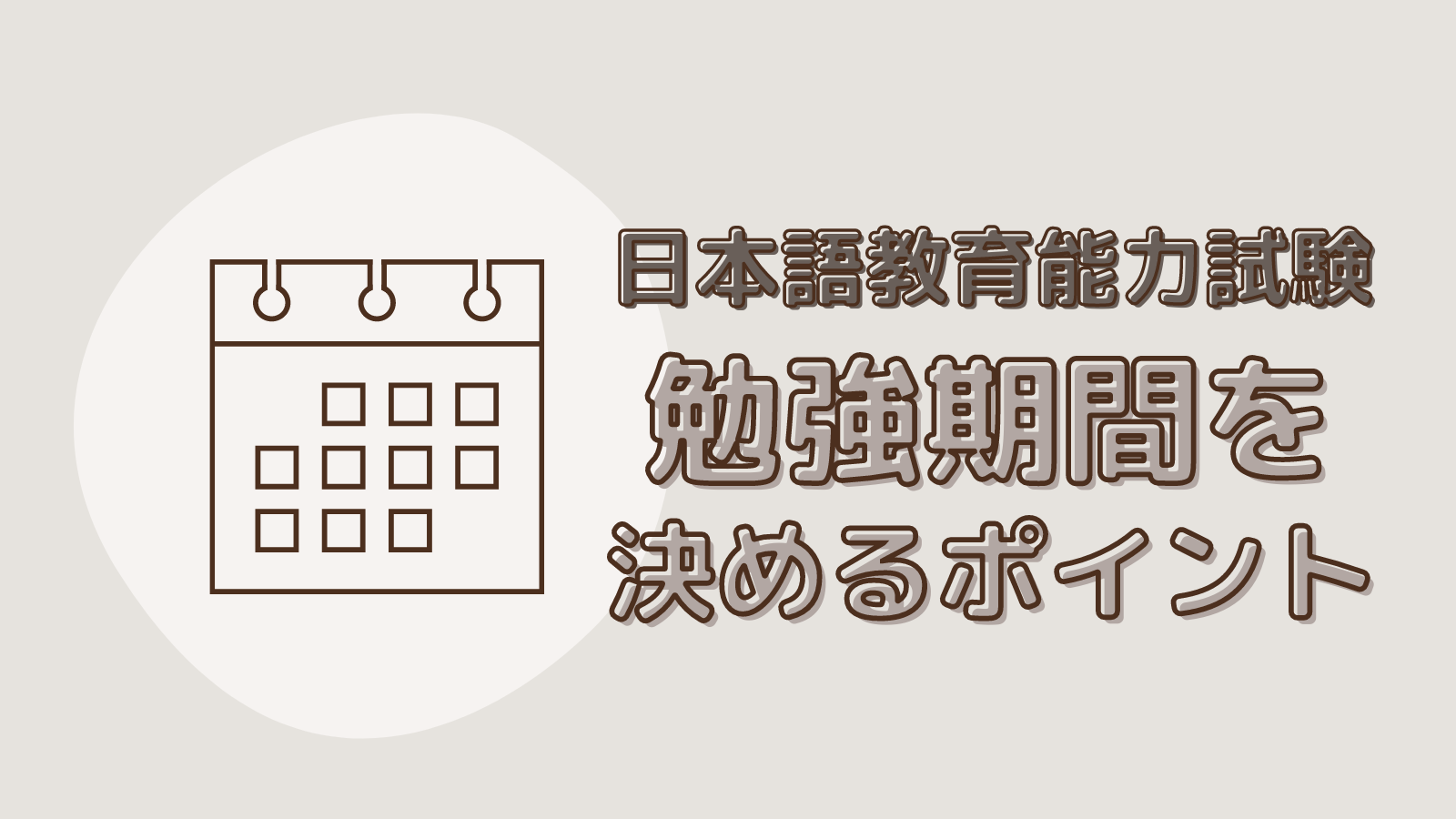



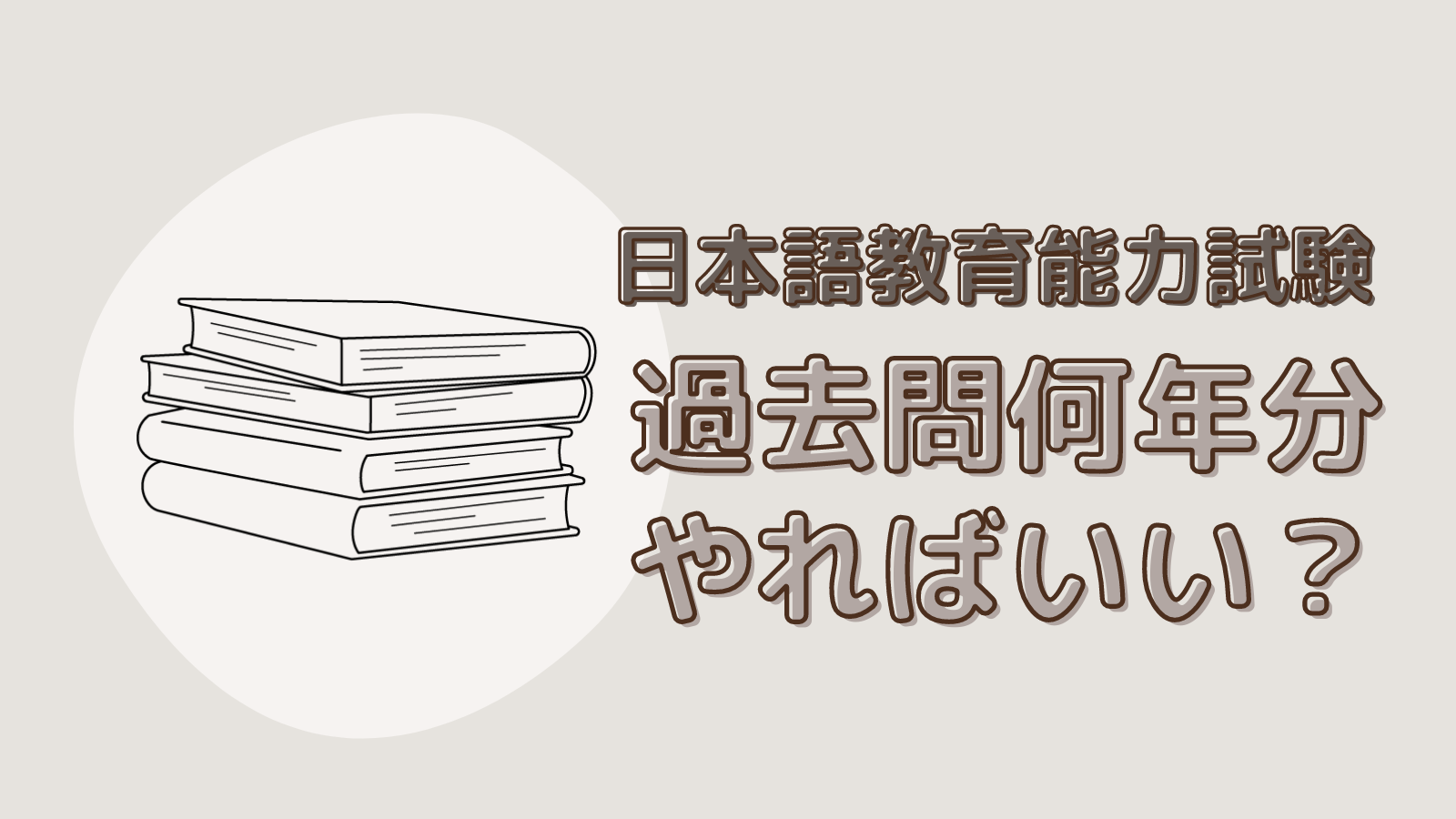

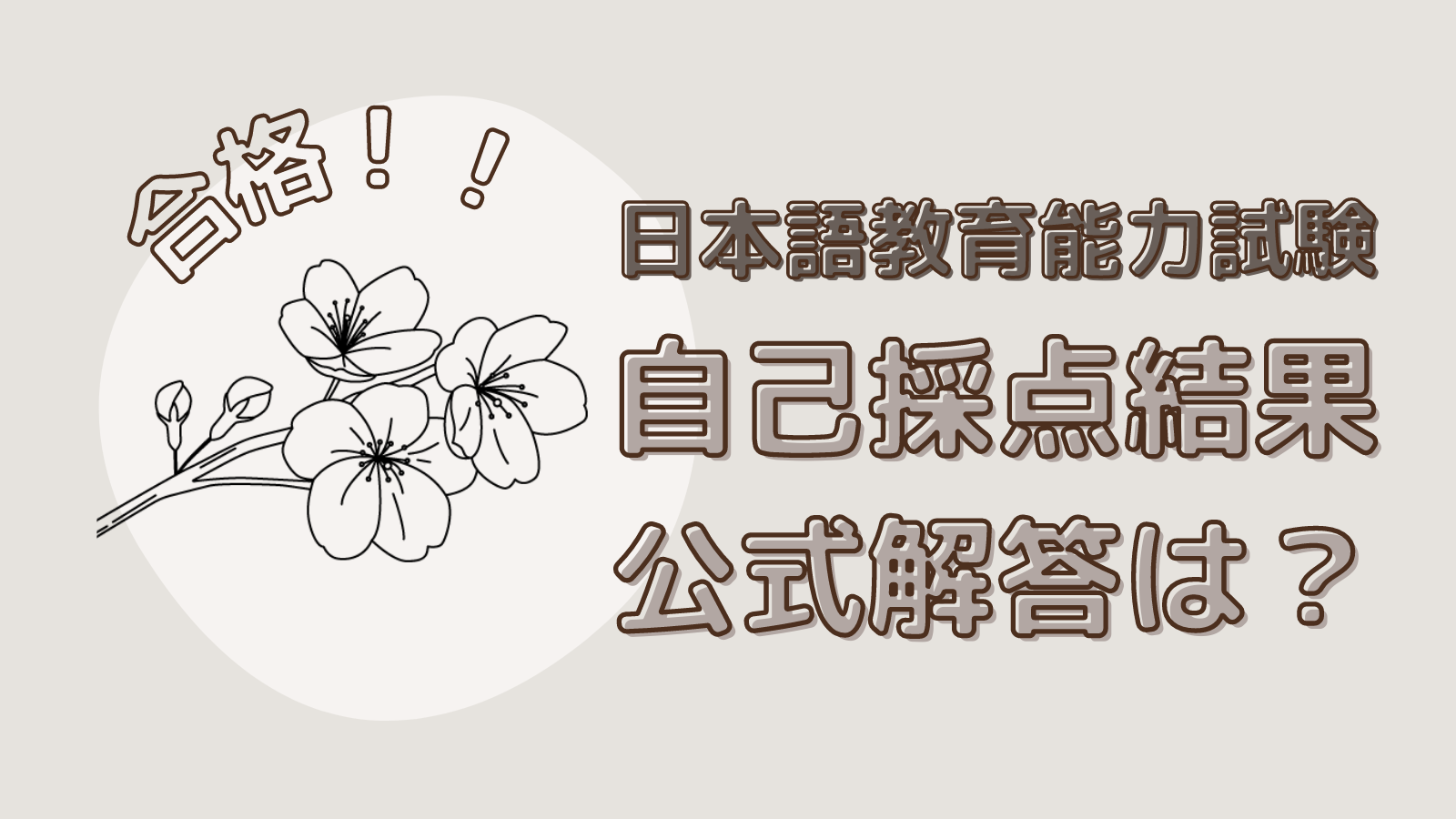
コメント