現在英文科在籍の人は、これから受ける授業を吟味することで、日本語教育能力検定試験の勉強を効率的に進めていけるかもしれません。
英語と日本語教育って、なんの関係があるの?と感じる人も多い思いますが、
実は英文科の授業には日本語教育に繋がるものが多く存在します。
 わたし
わたし私は大学4年次に日本語教育能力検定試験を受けました。英文科で、日本語教員養成課程(副専攻)のコースも履修していません。
ただ英文科の授業を履修していただけなのに、赤本を開いてみたら見たことのある内容がたくさんあったのです(驚)
そこで今回は、
- 検定試験に役立つ英文科の授業を知りたい!
- 英文科在籍で日本語教員養成課程も履修していないけど、検定試験に合格したい!
という方のために、日本語教育能力検定を受ける人が履修すると役立つ英文科の授業を紹介します。
検定試験に役立った英文科の授業
私が実際に履修した授業で検定試験に役立ったものはこちらです
- 英語学概論
- 談話分析
- 社会言語学
- 言語習得論
- コミュニケーション概論
- 英語音声学



それでは以下で詳しく見ていきましょう!
①英語学概論
英語学概論では主に「言語一般」分野の内容を幅広く学ぶことができました。
英語学概論ですから、英語学について広く浅く学んでいくイメージです。
一見日本語と関係なさそうですが、「言語学」という大枠の中の「英語学」のため、もちろん「日本語学」にも通ずるところがあります。



履修当時は日本語教育能力検定試験を受ける予定もなく、あまり興味も無かったので、ただボケっと授業を聞いていました。殴ってやりたいです。
以下はほんの一例に過ぎませんが、こんな感じです
※【】内は日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイド 第5版
- 語用論(ダイクシス・間接発話行為・協調の原理など)【言語一般】
- 音韻論(音声記号・音素など)【音声分野・言語一般】
- 形態論(拘束形態素/自由形態素)【言語一般】
- 統語論【言語一般】
- 意味論(ラング・パロール・プロトタイプなど)【言語一般】
どうでしょう?検定試験の勉強をしている人にはなじみ深い言葉ばかりですよね!
検定試験で問われる知識について学べたことはもちろん、言語学の全体像を知ることができたのも受講して良かったと感じる点です。
②談話分析
英語で談話分析の授業を受けましたが、赤本の内容と相違がありませんでした。
こちらも日本語教育能力検定試験では「言語一般」に振り分けられています。
- 会話の構造
- 隣接ペアのパターン
- 文同士の結びつき(結束性)
など赤本に載っているような内容を、授業では更に掘り下げ、実際の会話を用いて分析したりしました。



授業もすべて英語で受けたため、全く意味が分からず週10時間以上を予習復習に充てるという…coheranceってなんじゃい
正直地獄のようでしたが、この授業のおかげで検定試験で問われる談話分析の部分は少しの復習だけで済みました。
③社会言語学
社会言語学という名前の通り、社会と言葉の関係や、社会の中での言葉の用いられ方について学びます。
男女の話し方(内容)の違いや何がそうさせているのか、また相手に寄り添う話し方、逆に相手を遠ざける話し方など、言葉って本当に面白いなあと思った授業です。
日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイド 第5版
具体的な例を挙げると
- 言語接触(ピジン・クレオールなど)【言語と社会】
- 言語変種(高変種/低変種)【言語と社会】
- コードスイッチングとその目的・役割【言語と心理・言語と社会】
- ポライトネス・ストラテジー【言語一般】
- アコモデーション理論【言語と社会】
などでしょうか。
また東照二さんの『社会言語学入門<改訂版> 生きた言葉のおもしろさに迫る
入門書というだけあり、社会言語学の概観がわかりやすく説明されています。



社会言語学は、場面や相手に応じた戦略的なコミュニケーションを考える際にも役立ちます。日常生活やビジネスに応用できる部分も多いです
試験まで時間がない人や試験合格だけを目標にしている人にはお勧めしませんが、社会言語学に興味がある人、時間がまだまだあるよ~という人は一度読んでみてもいいかもしれません。
④言語習得論
言語習得論の授業では、「言語と心理」分野をほぼ網羅したと思います。
学習したのはこんな内容です(一部のみ)
- 外国語教授法【言語と教育】
- 短期記憶・長期記憶・ワーキングメモリ【言語と心理】
- バイリンガル教育【言語と心理】
- モニターモデル【言語と心理】
- 誤用(ミステイク・エラーなど)【言語と心理】
- 臨界期仮説【言語と心理】
どれも言語習得・獲得にまつわる内容で、検定試験でも絶対に押さえておきたい知識ばかりです。



今まで第二言語習得(SLA)分野で議論されてきたことや、語学学習において大切とみられているものを学ぶことができ、一外国語学習者としても非常に興味深い内容でした。
当時は検定試験を受ける予定がなかったため「へ~!!面白い!!」とただ授業を聞いていただけで、無理に覚えようとはしていませんでしたが、
この授業を受けたことで、外国語教授法やBICS・CALPなど検定試験で頻繁に問われる多くの知識を「聞いたことある」「なんとなく知っている」という状態にできただけでも、受講した価値が大いにありました。
⑤コミュニケーション概論
コミュニケーション概論からは主に「言語と社会」分野の内容をいくつか学べました。
- 伝達型モデル【言語と社会】
- 非言語コミュニケーション【言語と社会】
- 言語記号(ソシュール、サピア・ウォーフの仮説など)【言語一般】
- 異文化理解(エドワード・T・ホール、ステレオタイプなど)【言語と社会】
などなど。
コミュニケーション概論では、学んだ内容を自分の経験と照らし合わせて考えてみたり、また「どうしたらもっとうまくコミュニケーションがとれたのか」を考察したりしました。



実生活に直接結びつくものなので、「あ~だからあの時口論になっちゃったのか~」というような発見がたくさんあります。
また多様性の尊重といった異文化間コミュニケーションについても学びました。
特に日本語教師は学生とのコミュニケーションも欠かせませんよね。
コミュニケーション学は検定試験に必要な知識の獲得以上に、日本語教師として実践の場でも役立つのではないかと思います。
⑥英語音声学
日本語と英語の発音って全然違うじゃん??って感じですが
英語音声学を学んだことで日本語音声学をあまり苦労せずに理解できるようになりました。
具体的にはこんな感じ
- 発声の仕組み
- 発音記号
- 母音について(前/後舌、円唇/非円唇、低/中/高母音など)
- 子音について(調音点、調音法など)



破裂音・摩擦音・鼻音などの「調音法」や、母音発声時の「舌の前後位置・高さ」というような、日本語の音声学にも通じる概念を学べたのが良かったと思います
また [m]、[n]、[p]などは「マ行・ナ行・パ行かな?」と感覚的に想像できますが
[ʃ] [ŋ] [ʨ] [ʤ] ←こういうの、何?!って感じじゃないですか?
英語音声学ではこういった発音記号についても学んだので、日本語の音声記号を見たときもスムーズに理解できました。
~余談~
日本の大学でも英語音声学は履修していますが、留学先(台湾)で受けた英語学概論でもかなりみっちり教えられました。
例えば「Voiced Labiodental Fricative (有声歯茎摩擦音)」と言われたら即座に[v]だとわからなければならないなど…。
単位を取るために無我夢中で勉強しましたが、よく頑張って覚えたなあと思います(きつかったです)。



英語・日本語音声学は全く同じではありませんが、履修しておくと日本語音声学を学ぶときにとても楽に感じると思いますよ♪
まとめ:「聞いたことある」だけでハードルはぐっと下がる!
いかがでしたか?
- 英語学概論
- 談話分析
- 社会言語学
- 言語習得論
- コミュニケーション概論
- 英語音声学
以上からもわかる通り、日本語教育能力検定試験で役立つのは、
- 言葉そのものに関する授業
- 言葉と人の関係に関する授業
に多く、逆に英文学などの授業では検定試験に関連するものは少ないです。
本文内でも触れたとおり、私は上で紹介した授業のほとんどを、検定試験を受ける!と決める前に受講しています。
よって、「試験のために超真面目に授業を受けていた」わけではありません。
ですが、「あ、この教授法習ったな」「チョムスキーって聞いたことある、誰だったか忘れたけど…」というレベルにしておくだけでも検定試験へのハードルがぐっと下がります。
もちろん学校や先生によって学習内容に差があるため、まずはシラバスをよく見て選ぶことが大切です。
英文科で日本語教育能力検定試験を受けるよ!という人の、授業選びの参考になれば嬉しいです。
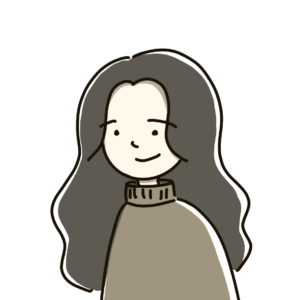
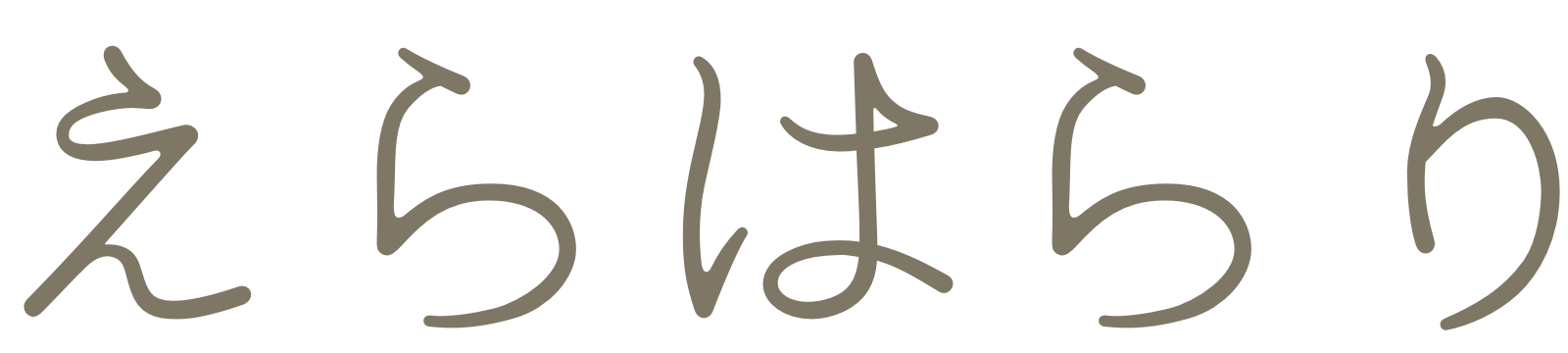


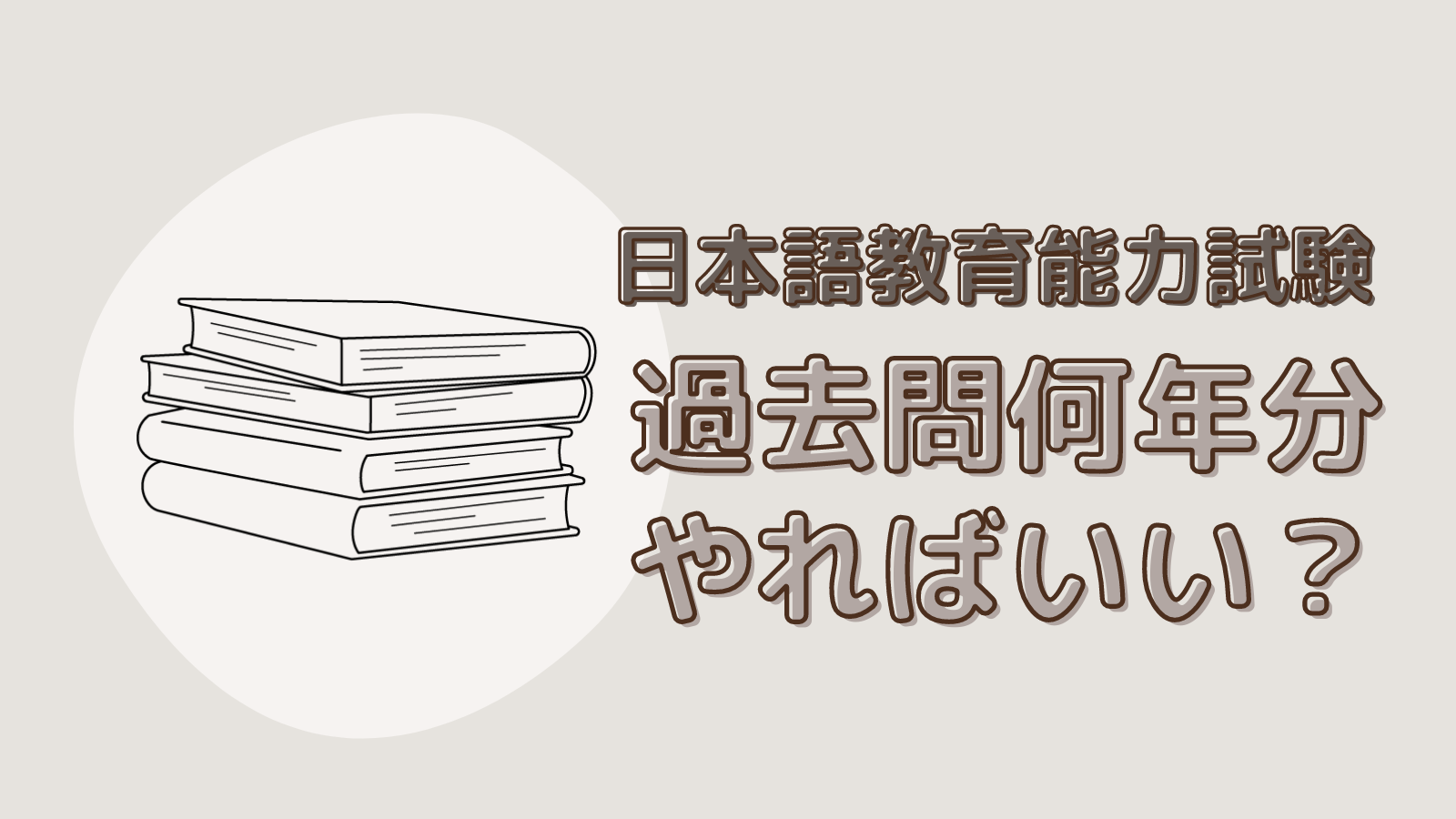

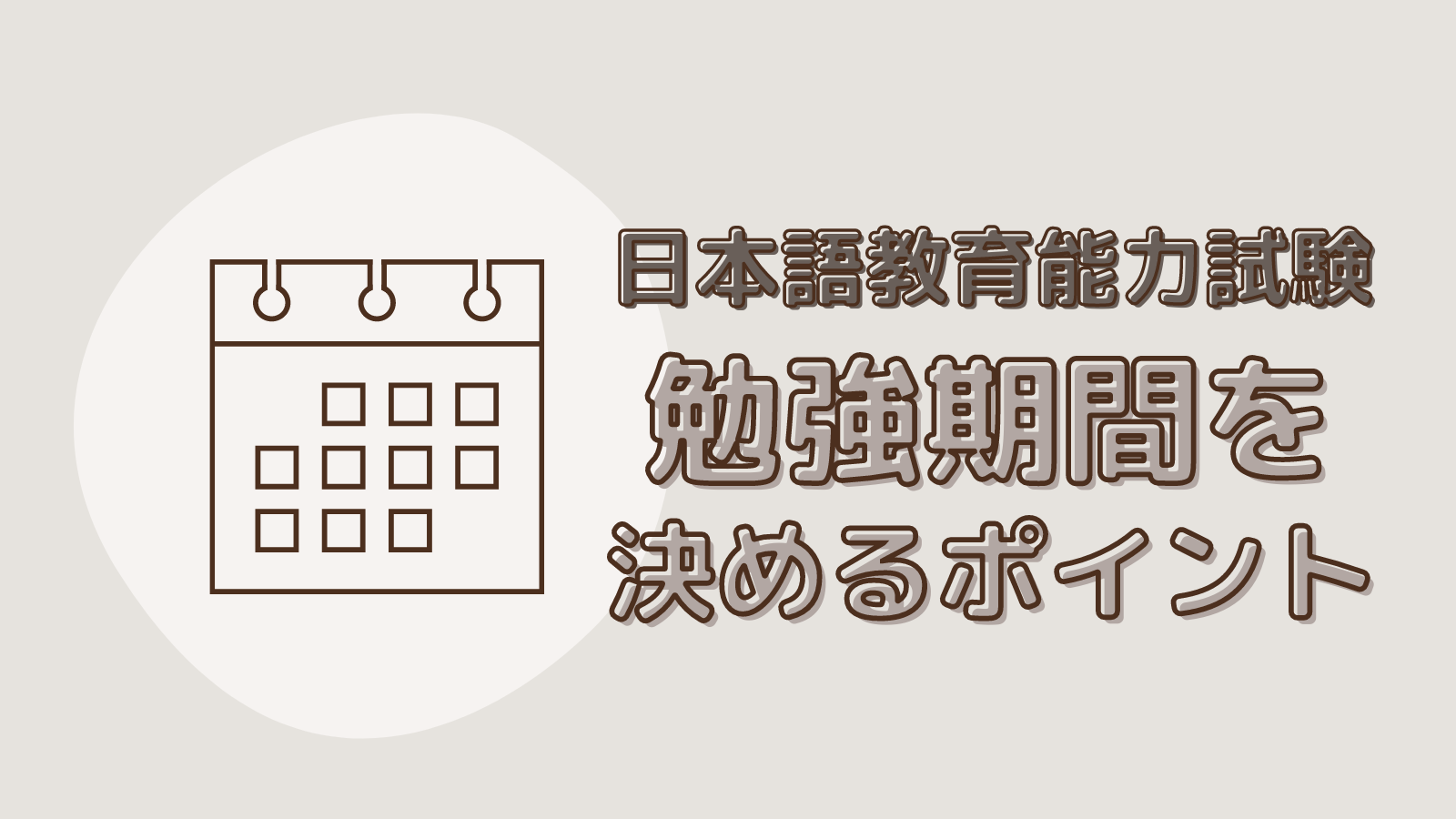

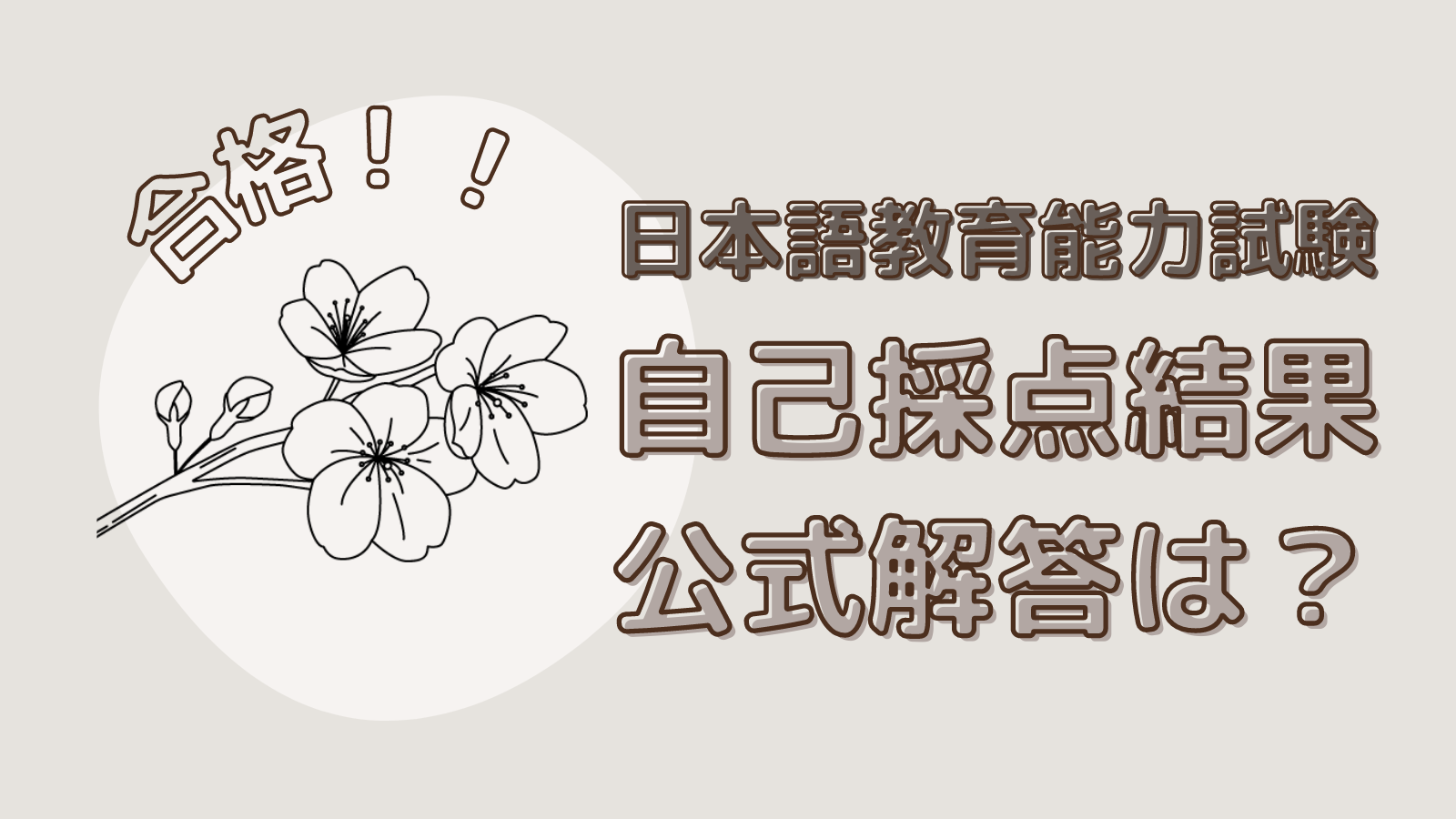
コメント